COLUMNコラム
在庫数を適正に保つための4つの発注方式とは
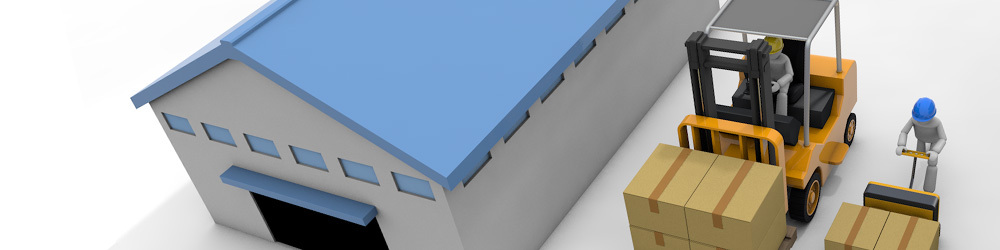
適切に在庫を管理するには、商品の性質に合った方法で発注を行うことが重要です。
商品の特徴にあった発注方法を選択することで、業務を効率化することができます。
今回はそれら4つの発注方式についてご紹介します。
定期定量発注方式
「定期定量発注方式」とは、一定量を一定のタイミングで発注する方式のことで、発注するタイミング・数量を考える手間がかからないというメリットがあります。
この発注方式は、安価で厳密な管理が不要な商品で用いられるケースが多いようです。
しかし、需要と供給が一定である必要があるのであまり利用されない方式です。
定期不定量発注方式
「定期不定量発注方式」とは、在庫状況・出荷量等を見て発注量を都度決め、定期的に発注する方式です。
この発注方式の特徴は、タイミングは一定ですが、都度発注量を考える手間がかかることです。
この発注方式に適した商品の特徴としては、比較的高価で、取扱量が多い商品などに用いられるケースが多いようです。
不定期定量発注方式
「不定期定量発注方式」とは、タイミングを決めずに決まった量を発注する発注方式です。
この発注方式の特徴は、発注点の管理などが必要となることです。常に在庫状況を確認し、必要なタイミングで決まった量を発注しますので在庫管理の手間がかかります。
この発注方式に適した商品の特徴は安価で厳密な管理が不要、需要供給が比較的安定した商品が多いようです。
不定期不定量発注方式
「不定期不定量発注方式」とは、変動する在庫量や出荷量を見ながら必要な時に必要な量を都度発注する発注方式です。
今までに説明していた発注方式とは異なり、場当たり的な発注を行うという意味ではなく、常に在庫状況の確認・需要予測を行いながら、適切な発注のタイミング・数量を管理するという方式です。
そのため、この方式で適切に在庫管理を行うには、在庫管理のシステム化が必要になります。
まとめ
商品の発注を効果的に行うためには、商品の特徴や需要と供給が安定しているかなどを考慮し、発注方式を検討すると良いでしょう。
また、在庫管理に関する業務を効率化し、在庫を減らすことでコストを削減したいという要望があれば、不定期不定量発注方式の導入を検討してみるのも良いかもしれません。
今後、サプライチェーンのIT化が進めば不定期不定量発注方式が一般的になると思われます。
在庫管理にかけられるコスト・手間・サプライチェーンにおけるシステム化の流れなどを考慮したうえで最適な発注方式を選択する必要があります。
物流ソリューション一覧
アトムエンジニアリングの物流ソリューションをご紹介します
課題 | 対応方法 | ソリューション |
|---|---|---|
| 誤出荷を防止したい | バーコード照合を活用した出荷検品の実施 | 在庫管理システム >> |
| 在庫の先入れ先出しをしたい | 入荷日・製造日・賞味期限などの日付をシステムで管理 | 在庫管理システム >> |
| 在庫管理の精度を上げたい | 倉庫作業を行う際に、ハンディターミナルなどでバーコードを照合 | 在庫管理システム >> |
| 商品のロット管理、賞味期限管理を行いたい | 入荷時にロットや賞味期限をシステムに登録し、履歴を管理 | 在庫管理システム >> |
| バーコードを利用した出荷検品だけ行いたい | ハンディターミナルやスマートフォンを活用したバーコード検品が可能な検品システムの導入 | 検品システム >> |
| トレーサビリティに対応したい | 商品の賞味期限やロット番号を管理し、出荷履歴が見えるシステムの導入 | 在庫管理システム >> |
| ピッキング作業の時間を短縮したい | 表示器を使用したデジタルピッキングシステムの導入 | デジタルピッキングシステム >> |
| 仕分け作業の時間短縮をしたい | 表示器を使用したデジタルアソートシステムの導入 | デジタルアソートシステム >> |


